「スマホ1つで、なんでもできる」
ChatGPTが文章を書いてくれる。
Canvaがデザインを仕上げてくれる。
でも、なぜか便利になればなるほど、幸福感が薄れてくる。
「本当に、便利な世界って幸せなの?」
AIが目まぐるしく進化を告げている今。
人間の生きる意味が、よくわかんなくなってきた。
暇と退屈の倫理学
國分功一郎は「暇と退屈の倫理学」でこう語っている。
「人間は、『結果』ではなく、『過程』にこそ意味を見出す生き物だ」と。
AIは、結果が欲しければすぐに回答する。
つまり、過程を飛ばし、結果が来る。
だから、AIを使い過ぎれば、人間は生きている意味を見出すことができなくなる。
めんどくさいことが嫌いな人間が、便利を追い求めた結果、不幸になっているという現実。
なんだそれ。
人間ってめんどくさいな笑
AIのおかげで理解できたこと
AIのおかげで、「身近なことが幸せなことだったんだな」って理解できた。
理由は、AIが「結果」を最短で導き出し、
「考える」「迷う」「選ぶ」
といった、人間の身近な営みが消えたからだ。
文章を書くことは、ただの作業ではなく、
「自分の頭の中を整理する行為」だった。
旅行の計画を立てるのは、
「ワクワクする時間」だった。
このように、人間の身近な営みは、しっかりと意味があったのだ。
それがAIによって、無くなった瞬間、
感情の入れどころがない、ただの作業みたいになってしまい、退屈になった。
ある意味、俺もAIになった感じ笑
このように、身近なこと(ある意味めんどくさいことも)全ては、意外と幸せの源だったんだなーっと思ったという話。
それでも便利を拒絶しない理由
でも、AIを全否定はしないよ。
便利さは人間が進化した証だし、もちろん救われる人もいると思うから。
ただ。
「何をAIに任せて、何を自分で行動するか?」
の選択をミスれば、不幸になるからね?って話。
選択する基準はね、
「考える」「感じる」
ことがある作業は、必ず自分の行動も入れること。
こればかりは、幸せを感じるためにもやるべきことなんだ。
未来に向けた「意図的な不便」のすすめ
私は最近、あえて遠回りして文章を書いている。
あえて、自分で調べる。
あえて、自分で考える時間を設ける。
この非効率の中に、
「俺は生きているんだな」
という確かな幸福感を感じる様になったからだ。
誰もが「AI」と言っている時代で、あえて、AIと距離を置くこと。
それは、時代に歯向かい、取り残されているように感じるかもしれないが、
幸福のために、あえて、立ち止まる勇気を持たないといけないのかもしれない。
AIの時代に不安を感じたら、『暇と退屈の倫理学』を読んでほしい。
國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学』では、
「暇や退屈こそが、人間を不幸にする構造」だと語られている。
そして、それは今まさに、AIによって暇が増えて、不幸を感じる人が増えてくる状況にある。
私がこの記事を書いたのも、AIが理由で不幸を感じることが増えたからだ。
AIは便利で良いが、それが「幸せの答え」ではない。
それに気づけた時は、ようやくAIの外で自由になれる。
もし、こういう感覚に少しでも共感したらら、
國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学』を読んでみてほしい。
この本は、まさに「便利の裏にある退屈」を解剖し、
「AI時代の不安」に、静かで深い答えをくれる一冊だからだ。

暇と退屈の倫理学 國分功一郎
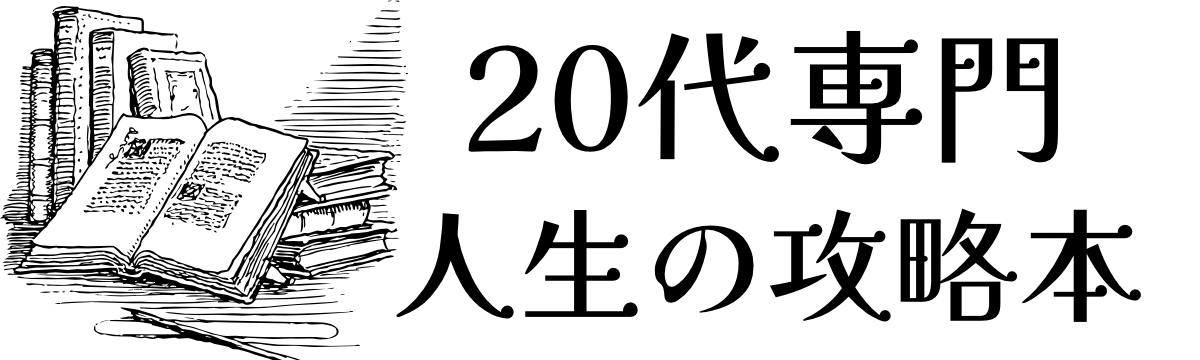


コメント